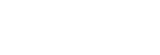政治レベルでは、加盟国を減らしたCPCの発効と3つの新加盟国の加盟に関する許容可能な規則の制定という問題を解決するための努力が続けられたが、他方で、共同体特許暫定委員会は、1985年会議後の数年間、2つの問題、すなわち、共同体特許明細書の翻訳に関する要件とCPCの財務規定の改訂の解決に集中的に取り組んだ。暫定委員会に報告する関連作業部会は、上記のトピックに重点を置くよう命じられていた。翻訳の問題については、産業界および特許専門家の代表が、欧州共同体特許はEPOの3つの公用語すべてで発行されるべきであると勧告した。暫定委員会は、内部討議の結果、この勧告は締約国のニーズを十分に満たさないため、受け入れられないとの結論に達した。暫定委員会にとって望ましいアプローチは、1975年版CPC第88条に従って翻訳に関する解決策を策定することであった。この条文は、締約国が共同体特許の明細書の翻訳について留保を表明し、共同体特許が当該締約国の公用語でない言語で発行された場合に、当該締約国のいずれかの国内言語による共同体特許の明細書のさらなる翻訳を要求する可能性に関するものである。
EC加盟国の数を減らしてCPCを発効させるという問題については、1987年に新たな提案がなされた。すなわち、1975年条約の加盟9カ国のうち7カ国(批准手続きが完了していないデンマークとアイルランドを除く)と、ギリシャ、ポルトガル、スペインの新規加盟3カ国である。しかしこの提案も、すべての加盟国の合意を得るには野心的すぎることが判明した。暫定委員会の協議でも合意が得られなかったため、ECの閣僚理事会でも協議が続けられたが、そこでも全加盟国が合意できる妥協案への道筋は見つからなかった。
同様に、財務規定に関する言語の問題も、暫定委員会のレベルで議論されたが、期待された肯定的な結果には至らなかった。言語留保を利用する国における共同体特許の翻訳文の提出条件に関する妥協案が、EEC加盟国の間で大筋で承認されたにもかかわらず、この妥協案に従うことはできないと明確に表明する国もあった。また、財務規制に関しても、1987年中に妥協に達することはできなかった。
このような試みが失敗に終わり、プロジェクト全体の成功のために、これらのトピックの緊急性が増していることに直面したため、委員会は、暫定委員会のレベルでこれ以上議論しても、行き詰まった状況を解決できないかもしれず、妥協のための可能な選択肢の報告書を閣僚理事会に提出し、政治レベルでさらに議論すべきであるという結論に達した。それ以降、共同体特許に関する未解決のトピックに関する議論は、理事会とその補助機関のレベルでのみ進められた。
1987年、ECの閣僚理事会は、共同体特許の導入に関する未解決の点に関する議論を引き継いだ。政治レベルでは、遅くとも1992年には欧州共同体特許が発効するとの確信が表明されていた。この時点では、1992年までに欧州域内市場が完全に実施され、これと同時に域内市場で共同体特許が利用できるようになることが期待されていた。
1988年、翻訳問題に関する討議において、共同体特許をすべての共同体言語に翻訳することが政治レベルで合意された。この基本決定による追加費用を補うため、特許権の存続期間の最初の年の更新料を減額し、それに応じて後の年の更新料を増額することが合意された。1988年中に解決できなかった未解決の重要な問題は、共同体特許の更新料を加盟国間で分担することであった。暫定的な解決策として、すでに批准手続きが完了しているか、近い将来に完了する見込みのある国(当時、EEC加盟12カ国のうちデンマークとアイルランドを除く10カ国がこれに該当した)に限りCPCを発効させるという提案に対して、加盟国の過半数がさまざまな議論の中で同意を表明していたが、すべての国による政治的承認は得られなかった。その結果、1988年中もこの点は未解決のままであった。
1975年と1985年の2回のルクセンブルク会議と、長年にわたってEC諸国の間で未解決のままであった一連の未解決の議題に関する長い討議を経て、共同体特許の実施に向けた次の有望な一歩が1989年に踏み出された。1989年12月15日、欧州域内市場における単一効特許保護へのマイルストーンが達成された。ルクセンブルクで5日間にわたって開催されたEC加盟12カ国の会議の末、欧州特許庁を通じて欧州単一効特許を取得できるようにする条約について合意に達した。これは、制度全体の関係者間の役割と責任の分担を明確にする上で、非常に重要な一歩であった。これは、共同体特許制度の最終的な実施に向けた出発点に過ぎないが、この試みは、共同体特許プロジェクトの作業が開始されてから約30年という年月を経て、真の突破口となった。
前章 第86章:単一効特許に向けて:1985年ルクセンブルク会議
次章 第88章:単一効特許に向けて:1989年ルクセンブルク会議の成果