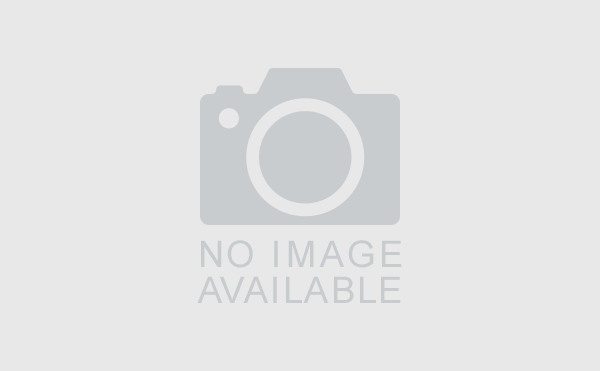第88章: 単一効特許に向けて:1989年ルクセンブルク会議の成果
1975年12月15日、当時のEEC加盟9カ国が共通市場のための欧州特許条約に合意した後、数年以内に欧州でこのような制度が迅速に実施されるとの期待は裏切られた。その主な原因は、加盟国のうちデンマークとアイルランドの2カ国における政治的・憲法的問題にあり、また、共同体特許の侵害と有効性に関する訴訟手続が、すべての加盟国が満足する形で決着していなかったことにあった。1985年12月に開催された第2回ルクセンブルク会議では、問題点の克服が試みられたが、期待された好ましい結果は得られなかった。その主な原因は、共同体特許を共同市場の一部にのみ導入できるかどうかという未解決の問題であった(このアプローチは、特にデンマークとアイルランドにおける問題を考慮して選択されたものであった)。さらに、新たにECに加盟する3カ国による共同体特許制度への加盟条件についても、全会一致には至らなかった。
1989年の第3回ルクセンブルク共同体特許会議で、大きな前進があった。 この会議で最も重要なことは、「共同体特許に関する協定」が確認されたことである。この協定は、主に1975年版のCPCを改訂したものであった。さらに、「共同体特許の侵害と有効性に関する訴訟の解決に関する議定書」、「共同控訴裁判所の特権と免責に関する議定書」、「共同控訴裁判所の規約に関する議定書」の3つの議定書が追加され、共同体特許はさらに強化された。さらに同協定には、欧州共同体特許法と欧州共同体の法秩序との関係、および欧州共同体司法裁判所の管轄権に関する規定も含まれていた。
また、その他の未解決のテーマについても、会議中にうまく明らかにすることができた。同会議は、共同体特許に関する収入と支出の配分について、すべてのEC加盟国が受け入れることのできる資金規模を決定した。これは、支出を差し引いた後に締約国間で分配される収入額を定めたものである。配分額と配分比率を決定する際の重要な要素は、EPOの予算は均衡を保つべきであるというEPCの原則に沿ったものでなければならないことである。さらに、支払額は、出願人にとって共同体特許を魅力的なものにしようとする締約国の政治的意思にも左右される。
共同体特許の翻訳要件についても合意に達した。請求項だけでなく、共同体特許全体の翻訳を、手続言語が公用語でないCPC締約国それぞれについての公用語の1つで提出しなければならない(CPC第30条)。1989年版におけるこの翻訳要件は、1975年版のCPCが課していたよりもかなり大きな経済的負担を特許権者に課すものであった。すべてのEC加盟国(1989年当時は12カ国)がCPC締約国となった場合、特許権者は共同体特許を8ヶ国語に翻訳しなければならず、これにより特許権者は翻訳のための追加的な経済的負担を負わなければならなかった。1975年版では、基本的にEPOの公用語に依存しており、EPOの作業言語と異なる国内言語を有する加盟国が、その国の1つの国内言語による翻訳を要求する可能性をオプション(必須ではない)として予見していた。一方では、特許文書をすべての共同体特許言語で翻訳するというアプローチは、特許権者の経済的負担を劇的に増加させることは明らかであったが、他方では、完全な翻訳パッケージを考慮すれば、当時すでに確立されていたEPCシステムと比較して、CPCの翻訳費用はそれほど法外なものにはならないはずだというのが加盟国の共通認識であった。また、EPOによる欧州共同体特許の中央管理は、かなりの節約をもたらし、その結果、追加的な翻訳の負担は高くなるが、利用者側にとっては穏当であり、許容できるものであろうという期待もあった。
欧州共同体特許の翻訳文は、特許付与の通知から3ヶ月以内に提出しなければならないが、EPCの規則のように各国特許庁に提出するのではなく、EPOにのみ提出しなければならない。特許出願人が期限内にすべての翻訳文を提出しなかった場合、付与手続完了後であっても、欧州共同体特許から欧州特許に変更することができる。各国語の翻訳文は、EPOが一元的に公開すべきである。EPOは、各国の産業財産権情報普及サービスにおいてさらに利用できるよう、翻訳文を各国の特許庁に提供すべきである。
1985年の討議ですでに検討されていたように、1989年の条約では、「共同控訴裁判所」(COPAC)と呼ばれる、共同体特許の侵害と有効性に関する訴訟の最終審判決を下す欧州の集中機関の設立が予見されていた。COPACはまた、2つの欧州特許条約が同じ基準に従って普遍的に適用されるようにしなければならなかった。訴訟に関する議定書の下では、共同体特許の侵害に関する第一審判決は、締約国の共同体特許裁判所が単独で下すべきであった。侵害訴訟は、原則として、被告が住所または施設を有する締約国の裁判所に提起されなければならなかった。各国の共同体特許裁判所が下した判決の執行については、管轄権及び執行に関するEC条約が適用されることが決定された。特許訴訟の効果または有効性に関する紛争は、共同体特許の場合、第二審かつ最終審の裁判所である共同控訴裁判所が決定すべきである。同裁判所の決定は、その後、各国の第二審裁判所および該当する場合には第三審の国内裁判所で行われるすべての訴訟手続を拘束する。COPACは本格的な不服申し立て手続きを行うべきであり、それはCOPACが把握した問題を検討し、事実と法律について裁定を下すべきだからである。
その結果、COPACは、特許性、効果、保護の範囲に関する問題など、CPCおよびEPCに関するすべての重要な実体的問題について最終的な裁定を下す責任を負うことになった。したがって、共同体特許訴訟におけるCOPACの法理が及ぼす影響は、共同体特許法の範囲をはるかに超え、欧州特許法(CPC、EPCおよび調和された国内特許法)の欧州および国内のあらゆる機関による統一的な解釈と適用に大きく寄与するはずである。
前章 第87章:単一効特許に向けて:1989年ルクセンブルク会議
次章 第89章:単一効特許に向けて:1989年会議後の数年間