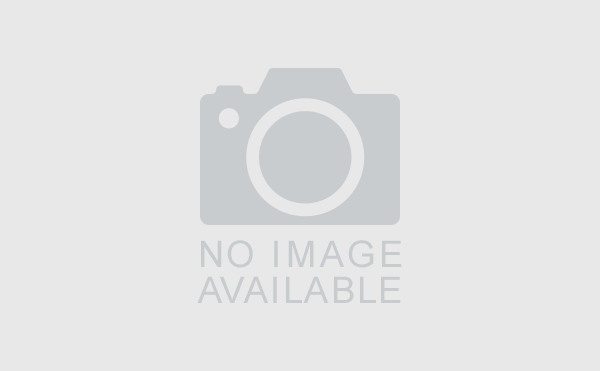第93章: 単一効特許に向けて:2000年以降の動向(2)
1999年の政府間会議の後、EPC締約国によって設立された作業部会は、欧州特許訴訟協定(EPLA)の草案を作成した。EPLAの議論は、欧州理事会や欧州委員会からではなく、( EPCの枠組みの中で)欧州特許庁の側から調整されたため、必然的に EPC加盟国も参加することができ、その結果、非EU加盟国も参加することができた。EPLAに対するアプローチは、共同体特許制度に関して議論されていた一連の規則の代替案として、あるいは少なくとも補足的な可能性として策定された。 協定案では、第一審裁判所(中央部1つと複数の地域部からなる)と控訴裁判所からなる欧州特許裁判所を想定している。特許裁判所は、欧州特許の侵害と有効性に関する紛争を解決する責任を負い、控訴裁判所は、欧州特許法の解釈について、助言を求めた各国の裁判所に助言を与える諮問委員会(Facultative Advisory Council)としての役割も果たすべきであるとされていた。
利害関係者、特許実務家、各国特許裁判官は、協議の過程で、協定に規定されたような訴訟制度を支持する意見を明確に表明したが、提案された協定とその背後にある制度は発効しなかった。2007年、欧州議会の法務部は、EPLAはEC条約第292条に違反するため、欧州共同体およびその加盟国は参加できないとの見解を発表した。その後2011年には、EU司法裁判所が、想定される裁判制度はEU法に適合しないとの見解を発表した。とはいえ、数年にわたる作業と作業部会の成果は、CPCに基づく欧州共同体特許とEPCに基づく欧州特許の両方に適用可能な統一裁判管轄制度を創設するための様々な問題や課題に関する有益な基礎知識をある程度は生み出すことにもなった。この作業部会の成果の一部は、後に、2023年に最終的に導入された欧州共同体特許をめぐる法的枠組みに反映された。
2007年4月、「欧州委員会から欧州議会および理事会へのコミュニケーション-欧州における特許制度の強化」が発表された。この文書は、2006年に行われた欧州における将来の特許政策に関する広範な協議プロセスについて言及している。このコミュニケーションは、欧州共同体特許に関するさまざまな未解決の課題を含めて議論を復活させた。まず第一に、コミュニケーションは、共同体特許の創設に対するコミットメントを確認した。同コミュニケーションの主な根拠は、欧州委員会が、事実上すべての経済分野の中小企業を含む企業、加盟国、および研究者や学者から、協議の過程で得た2500を超える個別の回答によって裏付けられ、また、それによって始動されたものであった。
同協議では、欧州において、審査、付与、付与後および訴訟手続において、シンプルで費用対効果が高く、質の高いワンストップ・ショップの特許制度を提供するための対策が緊急に必要であることが、疑いの余地なく示された。以前の試みで定義された翻訳手配の高コストが、利用者から強い批判を受けていることは明らかであった。協議の回答では、翻訳費用のほかに、裁判管轄制度の改善(統一特許裁判所制度の設立の可能性を含む)が最も重要な課題であると改めて指摘された。その結果、同コミュニケーションでは、共同体特許の創設と効率的なEU全域の特許裁判管轄の確立が一般的に取り上げられた。同文書には、EUの全公用語による特許情報の普及を促進しつつ、翻訳費用を削減することを目的として、翻訳協定のアプローチを加盟国と検討するという欧州委員会の申し出が含まれている。さらに、現在進行中の機械翻訳プロジェクトについても言及され、将来的にはこのようなシステムが特許文書の翻訳コストの削減に大きく貢献することが期待されていた。
協議の結果をさらに分析し、発展させるため、2008年上半期、理事会議長国であったスロベニアは、加盟国とともに、共同体特許に関する未解決の問題を集中的に検討した。2008年5月23日、欧州委員会が2000年に提案した簡略化された翻訳方式を基礎とし、一定の新要素を加えた共同体特許規則の改訂案が議長国から提出された。この提案によれば、出願人は、欧州連合の公用語であればどの言語でも欧州共同体特許出願を行うことができるようになる。この出願をEPOの公用語のいずれかに翻訳するための費用は、制度によって出願人に払い戻されるべきであり、特許明細書及び特許請求の範囲の全共同体公用語への翻訳は、特許情報の提供のためにのみ、特許出願の公告時に利用できるようにすべきであるとされた。これらの翻訳は、機械翻訳プログラムに基づく専門の中央サービスによってオンデマンドで行われるべきであり、 このようなプログラムには、国際特許分類システムにリンクされた技術語彙を有する電子辞書を使用すべきであるとされた。これらの翻訳は、情報の提供のみを目的として行われるべきであり、法的効力を有すべきではない。
また、共同体特許に関する紛争に限って、特許権者は、自己の費用負担で、侵害被疑者の要請に応じて、侵害が行われた国又は侵害被疑者が居住していた国の公用語への特許の完全な翻訳を提供すべきであることが規定されている。また、紛争が生じた場合、特許権者は、訴訟手続の過程で裁判所の要請があれば、訴訟手続の言語への完全な翻訳を提供しなければならない。つまり、実際には、紛争の場合にのみ、専門家による翻訳が必要とされることを意味する。通常の欧州共同体特許の付与手続では、特許出願にのみ専門家による翻訳が必要であり、その費用は制度が負担することとなる。
前章 第92章:単一効特許に向けて:2000年以降の動向(1)
次章 第94章:単一効特許に向けて:2000年以降の動向(3)