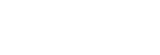1949年の提案の経験を念頭に置いて、欧州評議会は1950年に欧州特許専門家委員会(CEP)を設立した。同委員会は、欧州特許庁設立の可能性を特別に考慮しつつ、欧州における知的財産権分野の調和の可能性について調査することを基本的な任務として承認された。その作業の一環として、CEPは1953年と1954年の2つの条約の基礎を作成した。委員会は、特許庁の長官と加盟国の代表で構成され、国内法の様々な側面に関する研究に継続的に取り組んでいた。特に、他国で付与された国内特許の相互承認や有効性確認などのテーマに取り組んだ。また、実質的な特許法の統一や、独占的な実施権を有する統一欧州特許裁判所の設置も検討された。いずれのテーマについても、当初のアプローチでは、締約国の間で全会一致の支持を得ることはできなかった。主に、法律を統一する場合の複雑な状況を考慮して、これらのテーマに関する議論は延期された。このような結果を受けて、閣僚委員会は、まず第一に、発明の産業上の特徴、創造的努力、新規性、技術的進歩、請求項の記述の定義など、各国の特許基準の統一に焦点を当てるべきであるとの結論を下した。これらのテーマについて報告書を作成すべきであったが、進展は遅々としていた。
数年にわたる緩慢な進展の後、特許専門家委員会により、1962年に統一に関連するトピックに関する研究がまとめられた。この統一に関する様々な側面の研究結果に基づき、1963年11月、「特許実体法の特定の事項の統一に関する条約」(ストラスブール条約)が締結された。この条約は、後に欧州特許付与のための行政手続を一元化するための前提条件として、共通の実体的な欧州特許法の必須要素である新規性、進歩性、産業上の利用可能性を規定した。ストラスブール条約に記載され、定義されたこれらの3つの要素は、発明および発明保護の法的要件の統一的な適用を可能にする3つの重要な柱に相当する。この条約は、後に欧州特許庁の設立を成功させ、また最近の単一効特許の導入に不可欠な準備段階であった。
1959年、統一された特許制度の欠如に起因するヨーロッパにおける問題を検討することを目的としたEEC調整会合の機会に、特許専門家からなる作業部会が設置された。この作業部会は、産業財産権制度が必要であるかどうか、また、必要である場合には、異なる産業財産権制度の存在から生じる経済的格差が、域内市場に悪影響を及ぼし、競争を歪める可能性があるかどうかを分析し、どのようにすれば、このような経済的格差を縮小または解消できるかを検討する必要があった。グループの作業は、欧州特許法の調和が各国の法制度と共存しなければならない一方、EEC特許は単一的かつ自律的な権原を付与するという原則に基づいて進められた。このグループの作業の結果、1962年に欧州特許条約(共同体特許条約と理解される)の草案が提出された。この文書では、欧州特許庁からの不服申し立てを審理する管轄権を持ち、条約を解釈する権限を持つ欧州特許裁判所の設立が提案されていた。この裁判所と他の裁判所や国際裁判所との関係は、この文書には明記されていなかった。この目的のためには、別の提案を作成する必要があった。この最初の条約案は、当時のEEC加盟6カ国の間で集中的に議論されたが、合意には至らなかった。1962年に起草された条約が発効することはなかった。他の未解決問題のなかでも、条約をEEC加盟国だけに開放するのか、それとも他の国にも開放するのかという問題が、最終的に条約受諾の障害となった。しかし、この条約案は、一連の規則と解釈を定めた単一効特許に向けた最初の詳細な試みであったことは間違いなく、その後、一連の内容の修正に反映され、後に共同体特許条約の最終版にも反映された。
しかしながら、1963年のストラスブール条約採択後数年間は、EEC特許(EEC加盟国にのみ開放)または欧州特許(EEC非加盟国にも開放)の場合、特に国内法の調和の可能性に関して不確実な環境の中で、プロジェクトの進展は、ある程度、再び勢いを失った。しかし、ヨーロッパだけでなく世界的に経済が急成長しているという印象の下で、また、国際的な発展によって起こりうるヨーロッパ産業の競争力低下の懸念に直面し、EEC加盟国やEFTAの利害関係国は、少なくとも1960年代に議論された制度的なバージョンの一つである欧州特許庁のプロジェクトを進めることの緊急性をますます認識するようになった。
EEC加盟国の間で合意に達することができなかった共同体特許案に関して、ある種の不安と未解決のトピックが存在するこの雰囲気の中で、1965年の欧州評議会は、提案された条約のいくつかの側面について、より詳細な検討が必要であると決定した。しかし、未解決の点の明確化に向けた進展は遅々として進まず、複雑な状況を打開し、すべての加盟国が受け入れることのできる妥協案を見出すことはできなかった。そのため、1960年代後半には、EC特許プロジェクトがある程度勢いを失う一方で、同プロジェクトに代わる、あるいは、少なくとも同プロジェクトに追加的な、より国際的(欧州的)な環境、部分的に異なる法的環境、欧州における特許保護のためのより広い地理的機会を提供する制度を構築するというアイデアが勢いを増した。
前章 第80章:単一効特許に向けて:第二次世界大戦後の試み
次章 第82章:単一効特許に向けて:欧州(単一効)特許条約の第一次草案(1962年)